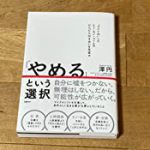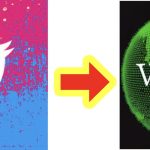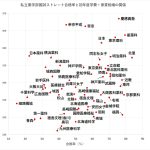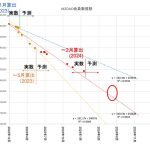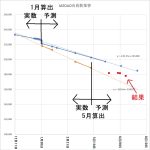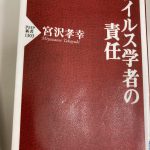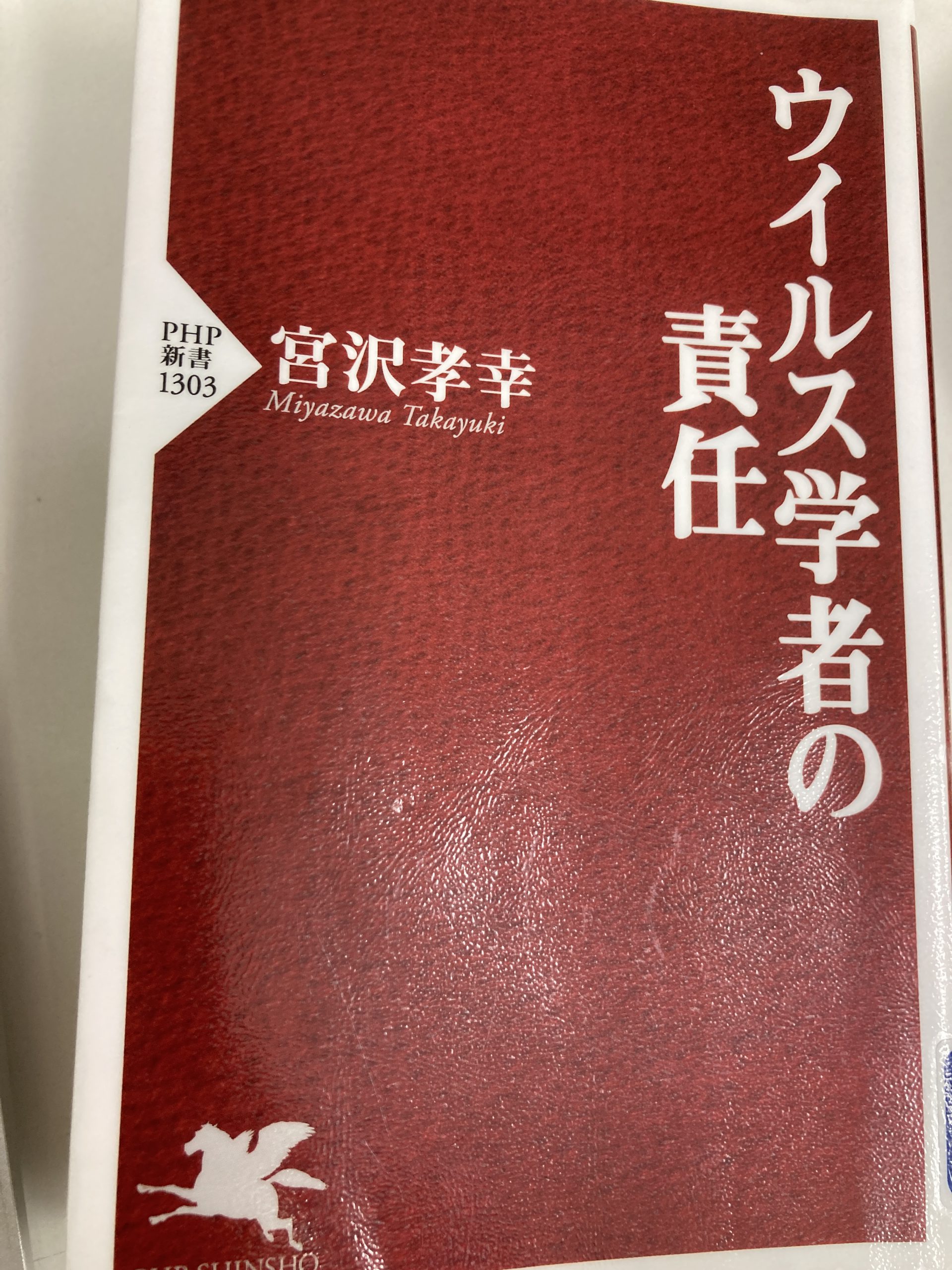
ウイルス学者の責任 宮崎孝幸 の読書感想文
さて、世間を騒がしている(?)京大の宮沢先生の著書
「ウイルス学者の責任」
を拝読しました
「京大おどろきのウイルス学講義」以来です、こちらも面白かった
 | 価格:880円 |
![]()
感想まとめ
・4回目のワクチンは打たなくていいな
・先生戦ってますね
・日本の検察、裁判て怖い
・東大に入ったらまた競争があるんですね
・生物学の発見は、単純作業の中にある
・「ダメな人」と言われている人を大事にする組織が強い
・4回目のワクチンは打たなくていいな
新型コロナウイルス4回目のワクチンを打つ人が増えてきた。
3回ともファイザー製を打った私であるが、4回目はもういいかな?と思っている。
くすりはリスク
この言葉に尽きる
4回目はファイザー製を打てるかわからない、ファイザーが後々
「あのワクチン大問題でした!すいません!」
となったらもうどうしようもない、、、
モデルナ製で同様のことが起これば自分は無関係である。
少しでもリスク回避はしておくべきだろうという結論
著書では動物のワクチンでがんを引き起こす遺伝子を見つけてしまった一説があった、ワクチンを打つことでいらぬ病気を増やしたくはない、、、
発見してしまったことをメーカー、役所に報告するも、「ことなかれ主義」によって請け合ってもらえない
生物製剤はわからないことだらけですので新型コロナワクチンにおいてもmRNAが大丈夫でも他の添加物に問題があったり、何か混入してたら嫌だなぁと思うのである
そもそも、もう5類でいいよね?と春頃から思っていたが、秋になってしまった
・先生戦ってますね
研究者として問題提起する場合、その問題により不利益を生じる人たちがいる、そしてその人たちの反発を必ず受ける
いくら問題視しても、現状問題ないのだからいいのでは?
と茶を濁したような回答をする人たちもがいる
先生が試薬メーカー、農水省、アメリカFDAと戦う生き様がわかる著書であった
研究をする上で客観的事実はとても大事なのであるが、それをよく思わない人もいる
私も経験があるのだが、学生時代、研究室で当たり前のように作っていたメインの物質が実はできていないことに気づく
一旦 合成を確認したもののその安定性にはかなり問題があり、いままで先輩たちがやってきた研究結果はいったい何だったのか?
そして、自分はいったい何をしているんだ?
と思った瞬間、ポッキリと折れたことがありました
科学的知見に基づき、ほぼ間違いなく白黒ついていても、それを声高らかに叫んではいけないことも世の中にはあるのか?
見えない力とと戦う先生の姿が想像できる著書でした
・日本の検察、裁判て怖い
栃木今市市小1女児殺害事件
今市市と聞いてどこかで?と思ったのですが、先日ちょうど
Youtube「街録チャンネル」で犯人の兄弟と名乗る人のインタビューを見たところでした
最高裁の上告を棄却されて刑が確定していますが、再審請求しているようですね
唯一の物的証拠が
被告人が飼っていた猫と被害者に付着していた猫の毛の「ミトコンドリア」のDNAが一致していた
あとは状況証拠や自白のみのようです
私も研究者の端くれです、ミトコンドリアDNAで個体が特定できないことくらい知っています
同じミトコンドリア持っている個体はたくさんいますからね
この鑑定は採用されませんでしたが、検察の都合のいいように鑑定はされているようです
ちょっと考えさせられてしまう内容でした
犯人が誰だとかは関係なく、カルロスゴーンの時も日本の取り調べには弁護士が立ち会えないという恐ろしい現実が逮捕後には待ち構えている
罵倒し、精神的に追い詰め、冤罪なのに罪を認めた方が楽になるような取り調べの道筋を彼らは何の疑いもなくやっているだろうか?
毎回、問題視されるもののなぜ改善されないのでしょうか?疑問です
もしも冤罪だとしたら恐ろしいです
東大に入ったらまた競争があるんですね
受験戦争を勝ち抜いて東大に合格しても、自分のやりたい学科に行くためにはそんな猛者どもとさらに競争して好成績を取らないと好きな学科に行けないという現実があることを知りました
宮沢先生は獣医師ですが、元は植物が好きだったようです
生物学の発見は、単純作業の中にある
大学院生、研究者なんて聞こえがいいかもしれませんが、確かに単純作業の繰り返しが多いです
その中に出てくるわずかな変化、思いもよらない変化にドーパミンを出す人たちなのですよね
「ダメな人」と言われている人を大事にする組織が強い
大学院生にもカースト制度のような見えない位があります
教授のテーマをやっている学生、准教授のテーマをやっている学生、助教のテーマをやっている学生、ポスドクのテーマをやっている学生
いろいろな研究室を渡り歩いてきた私にも見えていました
そんなカースト下位にいる学生でも研究報告会でしっかりと内容を発表できれば認められます
一方、そうでないと議論は頓挫してしまいます、ここでフォローしてくれる人がいればいいのですが、、、
私も博士号を取るために人とは違った苦労を重ねたと自負しています。
このまま諦めた方が楽だ、、、
そんな自分に手を差し伸べてくださる先生がいました
「意志あるところに道は開ける」
私の研究人生はこの言葉の通りでした